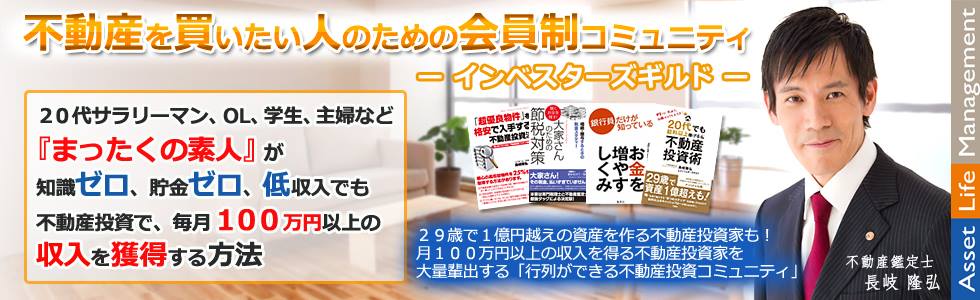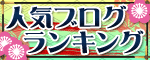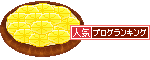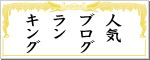Author Archive:
お金ってそもそも何?
3月 25, 2014
お金に「苦労」させられて、もう考えたくないという人もあります。
その一方で、お金が「有り余って」いても「まだまだ足りない」という人もいれば、必要最小限のお金だけで幸せな気持ちで暮らせる人もいます。
お金とはいったい何なのでしょうか……?
『お金の役割には、次の3つがあります。
①交換する手段
②価値を測る手段
③価値を貯める手段
です。お金は、この3つの役割を担うために生まれました。
原始社会をイメージしてもらうとわかりやすいですね。
その頃は、まだお金は存在せず、人々は欲しいものを得るために、物々交換という手段をとっていました。
山から採ってきた果物と、海で獲れた魚を交換する。でも、それぞれが必要とするものを、自分が持っているものと交換する物々交換には、いろいろな不都合があります。相手が自分の欲しいものを持っていない、あるいは自分が相手の欲しいものを持っていない。苦労して獲ってきた魚なのに。思ったよりいいものと交換できなかった、などなど、不満を抱えることも多かったでしょう。
また、「もの」は、いずれは腐ったり、原形をとどめなくなったりします。買ったときの価値が永遠に続くわけではありません。
このような時代を経て、
「いつでも客観的価値が変わらず」
「欲しいときに欲しいものと交換ができて」
「保管しておいても腐らない、消えてなくならない」
……そういうものとして「お金」が生まれました。』
(以上、長岐隆弘 著『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より、抜粋)
投資法・オフショアも不動産も?
3月 24, 2014
投資法といえば、FX、株、投資信託、先物、不動産などの方法が色々あります。
もしすであなたが何らかの投資法を実行済なら、それぞれの特徴を把握できていますか?
投資法の各々の特徴をしっかり掴んでいなければ、一時的にお金が増えたように思えてもまた何かで出費となる可能性もあります。
ではどんな投資法が有効なのでしょうか……?
『ただ、分散して投資したからといってもリスクがないわけではありません。
分散投資の罠については第1章の「分散投資では、お金を増やすことはできない!?」でお話しした通りです。
「集中投資もダメ、分散投資もダメならどうすればいいの?」
と思っていますね。ここから説明していきます。
分散投資の方法として有名なのが、「財産三分法」です。
財産三分法とは、自分の持つ財産を異なる性質を持つ3つの資産に分けて投資(保有)せよ、というポートフォリオ理論です。
一般には、「現金」「土地」「株」の3つの資産への分散という投資方法です。
ただし、分散投資には、この資産の分散以外の「分散」があります。
●時間の分散
●種類の分散
などです。』
(以上、長岐隆弘 著『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より、抜粋)
金融商品の種類を比較する前に
3月 23, 2014
銀行や証券会社などで、様々な金融商品を勧められることがあるでしょう。
その金融商品は何年もって、どのくらいになるのでしょうか。
保険の見直しが流行っていますが、金融商品の見直しもしたほうがよさそうです。
「いいですよ」と言われて投資を始めてみたものの芳しくない……というものがあるとき、いったいどうしたらいいのでしょう?
『今持っている資産のうち、このまま持っていても増えることが見込めないものについては、どんどん整理していきましょう。
まず、定期預金は、使用時期などの目的が特にない場合は、見直します。
次は、投資信託。信託報酬が高いものは解約します(「サンクコストは気にしない!」でしたね)。そのほか、必要のない金融商品は、いったんすべて現金化しましょう。
そして、資産の入れ替えを行います。
現金化してできたお金は、「お金の貯め方編」でご紹介した3つの口座のうち、半分を給与口座に、残り半分を貯蓄用口座に入金します。
給与口座には、毎月収入の10%を「不測の事態」や「冠婚葬祭」のために残していますね。そこに、今回整理してできたお金も加えます。
この口座には、理想としては給料の2年分くらいを貯めること、を目標にしましょう。それくらいあれば、例えば急な景気悪化の影響を受けて、万が一リストラされるようなことがあっても安心です。
ただ、給料の2年分というのはかなり大きな金額なので、そこまで貯めるのには時間がかかります。実際にはなかなか貯まらないにしても、目標としてその金額を目指す、という心構えが必要です』
(以上、長岐隆弘 著『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より、抜粋)
固定費を節約したい!
3月 22, 2014
固定費というのは、毎月必ずかかる費用のことですが、皆さんは月々どういうものに「必ず支払い」をしていますか?
「必要だからどうしようもない!」というものに、「光熱費」「食費」「車や携帯の維持費」「保険料」「返済」などがありますよね。
収入が限られるならどこかで節約しないとお金は貯まりません。
そこで、こうしてみてはいかがでしょうか……?
『毎月かかる固定費とは、住宅費(家賃または住宅ローン返済費用)、水道光熱費、自家用車があれば、その維持費などのことです。
これは、ほぼ毎月、決まった金額になると思います(エアコンの使用の多い時期には、光熱費がおおくなることもあるでしょうが)。
この口座に、収入の40%を上限としてお金を移します。
30万円の手取りの人だったら、ここに12万円が入ります。つまり、その範囲の中で固定費が収まるように、家賃や駐車場代などのバランスをとる必要があります。
固定費は変動が少ない=節約できる余地がない、ということになりますので、最初の段階で40%を超えることがないように、注意してください。
銀行員は、この鉄則をしっかり守っています。住宅費には、あまりお金をかけません。
社宅が充実しているから、という特殊な事情もありますが、家を買うにしても流行の高額物件などに手を出す人は少なく、郊外の手頃な価格の家を買ったり、親との二世帯住宅を建てたりする人がほとんどです』
(以上、長岐隆弘 著『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より、抜粋)
投資情報の収集はどうする?
3月 21, 2014
【投資情報の収集はどうする?】
よい投資先はないかと思っても、自分の身の周りだけでその情報収集をするのは、限られたものしかありません。
でも今は、インターネットというツールができて、自分の知り合い以外からもさまざまな情報が得られるようになりました。
しかし、インターネットからの情報というのは、「不特定多数」に向けて発信されている情報であり、なかには信憑性にかけるものもあるのが実際のところ……。
『銀行員には、同業他社(他の銀行)の人脈はあまりありません。
出会う場があっても、積極的にコンタクトを取らないようにしているくらいです。
もちろん、学生時代の友人や先輩などが、たまたま別の銀行にいたりすることもありますが、その場合でも、互いに自分の銀行の話題は出さないようなところがあります。
それよりも、銀行内の人脈づくりに注力します。
行内の派閥や人間関係、信頼できるかどうかなどを知って、確かな人脈を築くことは、今後業務を推進していく上で、非常に重要な役割を果たします。
実は、銀行員には、銀行内の人脈以上に大事にする人脈があります。
それは、「他業界の人脈」です。
銀行員は、他業界の人脈をとても大切にします。
メガバンクの行員ともなると、若いうちから他の会社の役員クラスや経営者と、直接つながることが多くなります。
金融以外の業界に関する「生の情報」を教えてくれるのは、そういう他業界の人たちです。経営者層の人たちなので、持っている情報の価値は、素晴らしく高いものです。』
(以上、長岐隆弘 著 『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より、抜粋)
自己投資の方法とは
3月 20, 2014
【自己投資の方法とは】
自己投資の方法というと、簡単に思いつくものといえば、習い事をする、資格取得する、美容や健康に気を付けるといったものではないでしょうか。
では、人が生きていくのに絶対に必要な「お金」を増やすためには、どんな自己投資が有効だと思いますか?
「銀行員」の場合には、こんな感じになっています。
『銀行員は、多数の金融商品を取り扱うという職業柄、多くの資格を取ることを求められます。
ファイナンシャルプランナー、金融商品証券外務員、証券アナリスト、貸金業務取扱主任者、宅地建物取引主任者など、数え上げればキリがないほどです。
それらの資格を取るたびに評価ポイントがついて、昇進につながっていく、というしくみになっています。
会社から命令されて、資格取得のために休日返上で猛勉強しているように見えますが、はたから思うほど、イヤイヤやっているわけではありません。
なぜなら、その勉強をすることに、あるメリットを感じているからです。
そのメリットというのが、「自己投資」です。
自己投資というのは、投資効率がいいと言われています。例えば読書の習慣がある人は、それだけで読まない人よりも成功しやすいというものです。
銀行員は、熱心に勉強しているので、どの金融商品が「買う側にとってトクなのか?」「売る側にとってトクなのか?」を熟知しています。
もちろん、それは業務上必要な金融知識を得たり資格を取るためなのですが、そうして得た知識や資格を、自己投資にも活用しているのです。』
(以上、長岐隆弘 著 『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より抜粋)
収入と貯蓄の比率って?
3月 19, 2014
収入があれば支出があるのは当然ですが、貯蓄や投資に回す人も多いことと思います。
しかし、いったい収入の「何割」を貯蓄に回せばいいのか、がわからない人もいるのも確か。
あまりにも貯蓄ばかりに精を出しても、衣食住を必要量揃えないというのであれば、健康などを害し、かえって医療費でかさみます。
では、いったいどれくらいの比率で貯蓄すればいい?
『収入があったら、まずは貯蓄、だといいました。
これは、できれば毎月、自動的に引き落としされるように設定しましょう。
自分で銀行へ行って、お金を下ろして別の口座に移す……というのは、毎月となると大変ですし、他の用事が入ったり、忙しかったり、面倒になったりして、途中でやめてしまう、なんてことになりかねません。
自動振り込みをやってくれる銀行もありますし、ネットバンキングなら、もっと手軽にそういった設定ができる場合もあります。
貯蓄する金額は、全体の10%を最低ラインと決めましょう。
手取りが30万円の人なら、3万円以上を貯蓄に回します。
最初は張り切っているので、どうしても、もっと高い金額を貯金しようと考えてしまいがちですが、ムリな金額はどこかにしわ寄せが来て、結果、失敗につながります。
なので、まずは10%から始めてください。
これでいいのかな? と思うくらいの金額で、長く続けることが、成功するコツです。』
(以上、『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より、抜粋)
お金をコントロールする財布術
3月 18, 2014
【お金をコントロールする財布術】
お金持ちの財布というと、とても興味がありますよね。
真似をして、プラダの財布を買ったところで「お金持ち気分」は味わえるでしょうが、実際、お金持ちになれるわけではありません。
ではどうしたら、自分のお財布、つまり自分のお金を確実にコントロールできるようになり、お金持ちに近づくことができるのでしょうか。
『管理して常に財布の中の金額を把握するためには、お札と小銭を分けておくほうが便利なのです。
3つ目の、領収書入れは、形はどんなものでもOKです。
レシートや領収書を保管するために使うもの。
財布と一緒に身につけておきたいので、古くなった財布や、前にでてきたポイントカード専用ケース(中身は捨てたはずですね!)を再利用してもいいですね。
何か支払いをしたときに、常に、
「お札は何枚使ったか(残りは何枚か?)」
「小銭をいくら分使ったか(残りはいくらか?)」
を確認し、
「レシートは、領収書入れに収納し、その日のうちに出して記録」します。
そうすることで、3つの財布が、いつでもスッキリと整理されている状態ができあがります。それが、お金の使い方をコントロールする、ということにつながります。
財布から出ていくお金には「投資」「消費」「浪費」の3種類があります。
浪費というのはムダ遣いのことなので、これは、投資に回す。
消費は生活に必要なものを買うことですが、努力して少しでも、投資に回す。
そんなコントロールを行うためにも、3つの財布の使い分けから始めましょう。』
(以上、『銀行員だけが知っているお金を増やすしくみ(集英社)』より抜粋)
融資の金利と銀行
3月 17, 2014
融資は銀行などの金融機関で行っている主な業務、という事は、もうすでに皆さんご存知だと思います。
ではこの「融資」、つまりお金を貸すことを別名でなんというかご存知でしょうか。
「与信業務」というのです。
与信業務というのはなぜかというと、「相手にお金を貸すこと」=「相手に信用を与える」という意味。
お金を貸すということは、相手を信用する、という事に他なりません。
逆に言えば、融資を受けたいなら「信用を勝ち取れる」ようにならないと無理のようですが……?
『よく、銀行員をからかう表現として、「雨の日に傘を貸さない」などと言われます。
しかし、銀行員からすると、実は、「そんなの当然でしょ!」と思っています。
誤解を恐れずに言うと、銀行の仕事というのは、お金がない人や足りない人にお金を貸すことではありません。
ビジネスとしてお金を貸しているので、「返せる人」にお金を貸すのは当然です。
ですから、
「晴れた日に、傘を持っている人に傘を貸す」のです。
これなら間違いなく傘を返してもらえそうですからね。
銀行員側のロジックでは、「借りたお金は必ず返す」のが当然です。
ここは、貸す側と借りる側での融資に関する受け取り方の間に、大きなギャップがあるかもしれませんね。借りる側は借りるまでは一生懸命ですが、返すことには無頓着な人も多いものです。
お金の貸し借りに無頓着な人は、お金を増やすことも難しい、ということを銀行員はわかっているのです。』
(以上、長岐隆弘・著『銀行員だけが知っている お金を増やすしくみ(集英社)』より、抜粋)

人気ブログランキングへ
定期預金の金利ってどう?
3月 16, 2014
“定期預金の金利、どこがいいかなあ。三井住友がいいか、それともゆうちょがいいか……”
お金は、入ってくる分すべてを使ってしまっていたら、一向に増えないというのはわかりますよね。
“そうか、だったら「とりあえず」定期預金にでも預けるか……”
と、思っているそこのあなた、これを読んでみればどうすればいいか、ヒントがつかめるかもしれません。
『金利を考える際に役に立つ、「72の法則」というものをご紹介しておきます。
これは、「72を金利の数字で割って出た答えが、預けた金額が倍になるまでの年数を表す」というものです。
例えば、バブル期の金利5.0%の場合なら、
72÷5=14.4
となりますから、14年ちょっとで倍になる、という計算になります。
現在のメガバンクの金利、0.03%ではどうでしょう?
72÷0.03=2400
そうです。なんと、2400年もかかってしまうのです。
これがネットバンクの金利の場合でも、
72÷0.3=240
どちらにしても、あなたが生きているうちに「倍返し」してもらうことは到底不可能。
ちなみに、ネットバンクとメガバンクの金利に10倍の違いがあるのは、それぞれが抱えるコストに差があるからです。
全国に支店を持ち、その店舗の賃料や人件費など、維持コストが莫大なものにあるメガバンクは、利益が出ても、預金者への還元はどうしても少なくなってしまいます。
このように定期預金は、「元本が保証されている」という安全の代償として、金利が低く設定されています。
だから、お金を増やしたい人にはまったく向かない金融商品、と言えるのです。』
(以上、長岐隆弘・著『銀行員だけが知っている お金を増やすしくみ(集英社)』より抜粋)